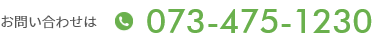言語聴覚士科
脳血管障害後遺症に対する訓練
「読む、書く、聞く、話す」「上手く話せない」といった言語機能の障害に対し、コミュニケーションの改善を目指して取り組みます。
「食べるときにむせる」などお食事に困難を感じている方に対しては、安全に美味しく食事が行えるように援助します。
「言語聴覚療法=言葉と聞こえの訓練」というイメージがありますが、それだけではありません。
脳卒中などの病気や事故による脳の機能障害によって、社会生活を送る上で他人には見えにくい困難を抱える様々な患者さんのリハビリテーションを行います。
高次脳機能障害に対する訓練
例えば、スーパーでリンゴを買うときに、どんな脳の働きが必要でしょうか。
- 買い物を計画し、スーパーへたどり着くこと。
- 買うものはリンゴだと記憶すること。
- 案内図を見て売場の位置が理解できること。
- 店員さんに尋ねること。
- レジでお金の計算ができること。 等

一見簡単に見える事でも、様々な脳の機能が働きあうことではじめて可能となるのです。
当院では、コミュニケーションに不自由さを感じておられる患者さんに寄り添うことを大切にしながら、リハビリテーションを進めていきます。
嚥下障害に対する訓練

食事中にむせる、食べ物がのどにつっかえて飲み込みにくい等、食事に不安を感じる患者さんに対して、安全においしくお食事を楽しんでいただけるよう、リハビリテーションを行います。
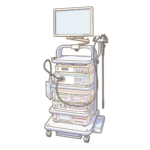
X線による嚥下造影検査(VF)や内視鏡検査(VE)を使用して、のどの動きを詳細に検査し、安全にお食事をとることができるよう、リハビリテーションを進めていきます。
当院では、在宅で過ごされる患者さんや当院を退院された患者さんにも利用していただけるよう、外来診療やデイケア、訪問によるリハビリテーションも行っています。

また、和歌山失語症友の会「紀の国会」の事務局を設置し、患者さんやご家族同士の交流を図り、活動する場を提供しています。
検査、治療機器の紹介

◎Vital Stim(バイタルスティム)
嚥下(飲み込み)困難を改善するために開発されたもので、喉の筋肉に 低周波(微弱な電気)を当てることにより、嚥下に関わる筋肉を刺激します。
バイタルスティムの活用により喉の筋肉を鍛えるための複雑な運動が 難しい患者さんも、喉の筋肉を動かし鍛えることが可能です。

◎舌圧計
舌圧とは舌が口蓋(上あご)を押し付ける力の事を言います。
舌圧は脳血管障害や廃用(活動性が低下して筋力や心肺機能が低下した状態)による筋力低下により低下し、舌圧の低下は嚥下機能の低下につながります。
舌圧を測定する舌圧計を訓練や評価に用いて舌機能評価の指標とします。
小児リハビリテーション

子どもの発達及び言葉の治療・相談に取り組んでいます。
1982(昭和57)年に口唇口蓋裂の方のことばの訓練から開始し、以後、子どもの発達障害、構音障害、吃音など、広範囲な検査・治療・相談にあたっています。
子どもの言葉を育てるために大切なことは、ご家族、特にご両親との信頼関係をもとに子ども自身が自分の手、足、身体を使って、外の世界に働きかけることであると考えます。
当院には、検査・訓練を行う個別訓練室と聴力検査室、そしてプレイルーム(おもちゃで遊ぶ部屋)があります。
「3歳になってもことばを話さない」というご相談では、子どもの普段の様子をご家族からお聞きし、それから一緒に遊びます。子どもにとって、遊ぶことは立派な仕事です。これらの訓練ややり取りを通して、ソーシャルスキルの獲得を図っていきます。

吃音治療・訓練のご案内
当院では、吃音症状に対して言語聴覚士が幼児から成人まで各ライフステージに沿った支援を行っています。
令和4年度より従来の吃音治療に加えて、「リッカムプログラム」を用いた訓練を開始しました。
リッカムプログラムとは
- このプログラムは、家庭でご両親との練習(会話・やりとり)によって行われるものです。
- 毎日10~15分、ご家庭で楽しく練習します。
- 練習では、お子さんの発話に対して効果的な「言葉かけ」と行います。「言葉かけ」の内容は病院での訓練の際に、セラピストがその都度お伝えします。
- 吃音のない、あるいは一般の方がほとんど気づかない状態をめざします。
対象となる方
- 吃音症状のある幼児(主に6歳まで、場合によっては小学生まで可)
- 平日 週1回~月2回 来院が可能な方
訓練のご希望がありましたら、当院(TEL 073-475-1230)までご連絡ください。詳しくは、初回来院時もしくはお電話にて川口(言語聴覚士)までお問い合わせください。
言語療法士の紹介